一級建築士 合格体験記4〜学科試験日〜
アラサー兼業主婦のミケネコです。
平成28年度に受験しました。
一級建築士試験の学科当日の様子をお伝えします。

学科試験当日
一級建築士の学科試験は、毎年7月の第4日曜日に行われます。
ミケネコは、試験会場近くのホテルに前泊したので、試験会場に1時間前に着くようにチェックアウトしました。
ホテルから試験会場に向かっていると、同じ受験生だと思われる男性が複数いました。
試験会場には既にたくさんの受験生がいて、最後の確認をしていました。
試験データで、男女比は約7:3と出ており、その通りに感じました。
年齢層は、同世代だと思われる受験生が多くおり、落ち着けました。
ミケネコは、途中で配布された日建学院や総合資格のチラシを一通り読み、計画と環境設備のまとめノートを見直しました。
注意事項等説明が始まり、いよいよ学科試験が始まります。シーンとした時間が長く感じました。
計画・環境設備
・計画(学科I)20問
・環境設備(学科II)各20問
・2時間
時間は余裕があり、何度か見直すことが出来ました。
計画の1問目は、まさかの『談合』が出題されました。試験勉強をしていなくても大丈夫そうな問題です。
1問目が全く解らない問題か、自信がある解答を出来るかで、その後の精神面にかなりの影響があると思います。
計画は、新傾向の選択肢も有り2択まで絞り込むことが出来つつ、自信の無い問題が複数有り、足切り点に達しているか心配でした。
環境は、やや易しく感じ、手応えを感じました。
一応、望みを持って終えることが出来ました。
法規
・法規(学科Ⅲ)30問
・1時間45分
45分の昼休憩を挟んで法規が始まります。
休み時間中に、来る途中のコンビニで購入したおにぎりを食べながら、まとめノートを見直しました。
計画や環境設備の解答が気になりますが、気持ちを切り替えます。
試験前に、試験官による法令集チェックが行われました。全ての受験生の法令集をチェックしていたので、25分という時間も納得です。
ミケネコは、仕事で意匠設計をしていたので、実際に法令集は良く使っていましたし、面積や高さの問題も難なく解くことが出来ていました。
この1年間の勉強で、あまり法令集を引かずに答えが導き出せるようにもなりました。
実際の試験でも法令集はあまり引かず、自信がない問題でも確実に正解する為に法令集を使いましたので、時間が足りなくなることはありませんでした。
法規は手応えを感じて終えることが出来ました。
構造・施工
・構造(学科Ⅳ)30問
・施工(学科Ⅴ)25問
・2時間45分
20分の休憩後、最後の試験が始まりました。
ミケネコは、施工→構造(文章)→構造(計算)と言う順番で解きました。
精神面で不利にならないように、時間は余裕がありますし、苦手分野を後にしています。
とは言え、構造が1番苦手で、次に施工が苦手分野でした。
案の定、施工も自信がなく、次の構造(文章)もボロボロで、構造(計算)なんて悲しくなりました。
構造(計算)は全問正解できる問題と言われていて、ミケネコも多くの勉強時間をかけました。
それなのに、全然自信がありません。
施工と構造(文章)の見直しをしてから、最後まで構造(計算)に試験時間を費やしました。
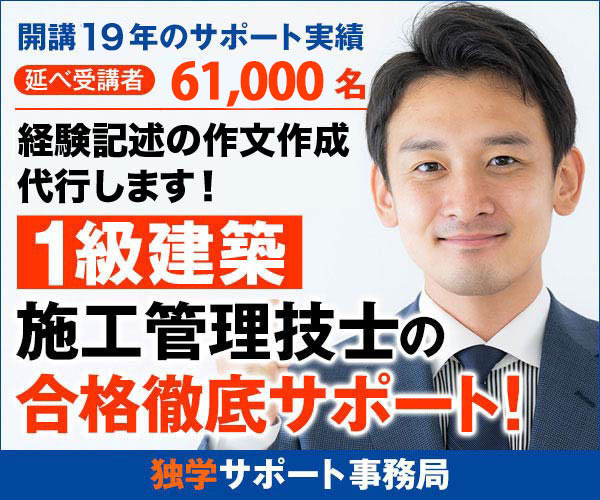
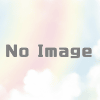


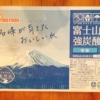




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません